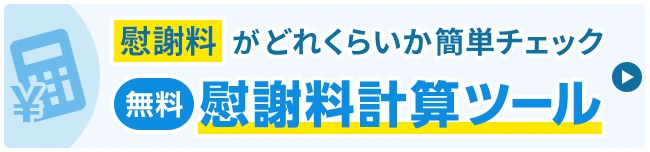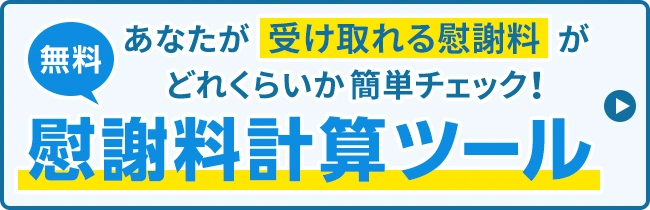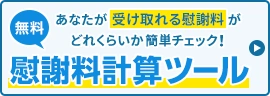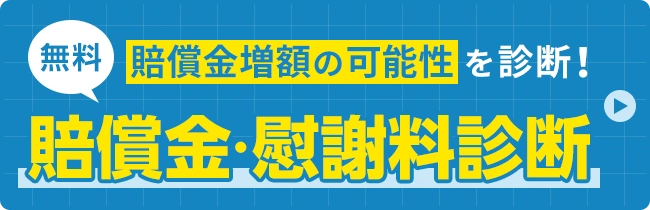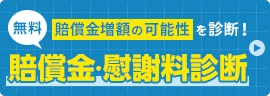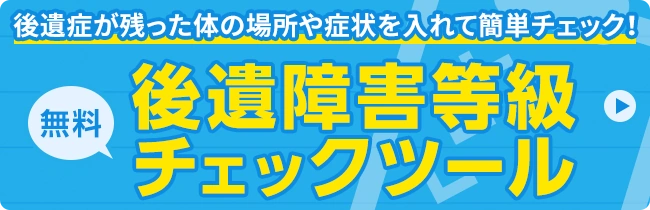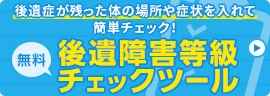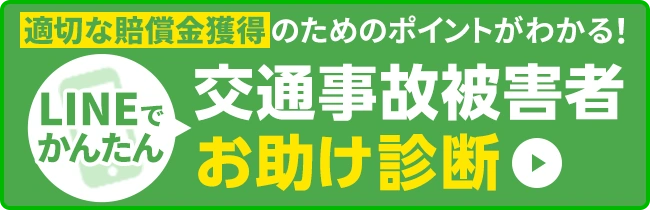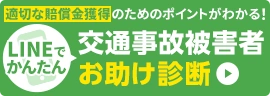併合、相当、加重って何?知っておきたい後遺障害等級認定のルール

交通事故にあったとき、複数の部位を負傷する方も多いでしょう。そのような場合、ケガの治療が終わったものの2つ以上の後遺症が残ってしまうことも少なくありません。
このような複数の後遺障害の等級認定に際し、「併合」という認定ルールがあります。
後遺障害等級が併合された場合、後遺障害慰謝料や逸失利益が増額する可能性がありますので、その可否は重要といえます。
また、「相当」や「加重」といった言葉について、後遺障害診断書に記載されているのを見たことがあるかもしれません。
今回の記事では、後遺障害等級認定に深いかかわりのある「併合」・「相当」・「加重」の概要や、認定結果とのかかわりについて説明いたします。
- この記事でわかること
-
- 後遺障害等級の「併合」の意味
- 後遺障害等級における「相当」の意味
- 後遺障害が「加重」と評価された場合の保険金支払いのルール
- 後遺障害慰謝料の相場
- 目次
交通事故被害の
無料相談は
アディーレへ!
後遺障害等級認定のルール「併合」・「相当」・「加重」とは
「併合」・「相当」・「加重」とはどのようなルールなのか、どのように適用されるのかについて解説いたします。
併合とは
併合とは、異なる部位の障害が複数残った場合の、後遺障害の認定方法です。具体的には、複数ある後遺障害のうち、もっとも重い等級が繰り上がります。
併合の基本的なルールは次のとおりです。
- 5級以上の後遺障害が2つ以上ある場合には、もっとも重い後遺障害等級を3つ繰り上げる
- 8級以上の後遺障害が2つ以上ある場合には、もっとも重い後遺障害等級を2つ繰り上げる
- 13級以上の後遺障害が2つ以上ある場合には、もっとも重い後遺障害等級を1つ繰り上げる
- 14級の後遺障害が2つ以上ある場合には、14級のまま
ただし、すべてのケースで併合というルールが適用されるわけではありませんので、注意が必要です。
「後遺障害認定の結果が届いたけれど、内容がよくわからない」という方は、弁護士に相談することをおすすめします。
相当とは
相当とは、後遺障害等級表に定められていない障害についての、後遺障害の認定方法です。
後遺障害等級表に定められていない後遺障害について、その障害の程度に応じた後遺障害等級が認定されます。
例としては、嗅覚や味覚の喪失や減退が挙げられます。
また、異なる部位ではあるものの、同じグループ(系列)に属する障害を併合した場合も同様です。
たとえば、右膝の関節機能障害(12級)と右足の関節機能障害(11級)を併合し、11級を1つ繰り上げて10級相当とする場合です。
主な具体例としては、以下の後遺障害が挙げられます。
- 嗅覚脱失や味覚脱失(12級相当)
- 嗅覚減退(14級相当)
- 外傷性散瞳(11級相当、12級相当、14級相当)
- 上肢における動揺関節(10級相当、12級相当)
- 下肢における動揺関節(8級相当、10級相当、12級相当)
加重とは
加重とは、既に障害のあった同一部位について、交通事故により障害の程度が重くなった場合の、後遺障害の認定方法です。
この場合、「交通事故で発生した障害の等級」と「交通事故前からある障害の等級」それぞれの後遺障害等級が認定されます。
両等級において加重と認定された場合には、「交通事故で発生した障害の等級に対応する保険金額」から「既にある障害の等級に対応する保険金額」を控除した保険金額が支払われます。
「交通事故にあう前からある障害」が交通事故を原因とするか、生まれつきのものであるか、といったことは問われません。
たとえば、昔の交通事故で14級の後遺障害が認定されており、今回の事故で同一部位について12級の後遺障害が認定された場合、自賠責保険からは12級の保険金額から14級の保険金額を控除した金額が支払われます。
後遺障害等級が認定された場合の慰謝料について
慰謝料には3つの基準がある
後遺症慰謝料の算定においては、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの基準が存在します。
自賠責基準は、自賠責保険の支払の基準です。自賠責保険は被害者救済のため最低限の補償をするものですので、通常、3つの基準のなかではもっとも低額となります。
任意保険基準は、各任意保険会社独自の基準です。任意保険基準は公表されていません。
弁護士基準は、過去の裁判例をもとに設定されている基準で、通常、3つの基準のなかではもっとも高額となります。
後遺症慰謝料について、自賠責保険基準と弁護士基準を比較すると、次のようになります。
介護を要する後遺障害
| 後遺障害等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 第1級 | 1,650万円(1,600万円) | 2,800万円 |
| 第2級 | 1,203万円(1,163万円) | 2,370万円 |
- ※()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合
介護を要さない後遺障害
| 後遺障害等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 第1級 | 1,150万円 (1,100万円) | 2800万円 |
| 第2級 | 998万円(958万円) | 2370万円 |
| 第3級 | 861万円(829万円) | 1990万円 |
| 第4級 | 737万円(712万円) | 1670万円 |
| 第5級 | 618万円(599万円) | 1400万円 |
| 第6級 | 512万円 (498万円) | 1180万円 |
| 第7級 | 419万円 (409万円) | 1000万円 |
| 第8級 | 331万円 (324万円) | 830万円 |
| 第9級 | 249万円 (245万円) | 690万円 |
| 第10級 | 190万円 (187万円) | 550万円 |
| 第11級 | 136万円 (135万円) | 420万円 |
| 第12級 | 94万円 (93万円) | 290万円 |
| 第13級 | 57万円 | 180万円 |
| 第14級 | 32万円 | 110万円 |
- ※()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合
後遺症慰謝料以外に請求できるもの
交通事故の被害者は、後遺症慰謝料以外にも次のような損害について、加害者に請求することができます。
- 治療費
- 入院雑費
- 通院交通費
- 休業損害
- 入通院慰謝料
- 逸失利益 など
交通事故の損害賠償請求において、加害者側へ請求し得る損害項目は多岐にわたります。相手方保険会社からの示談の提案内容について、少しでも疑問がある場合には、交通事故に詳しい弁護士に相談した方がよいでしょう。
まとめ
後遺障害の認定には「併合」・「相当」・「加重」というルールがあり、これらのルールは、交通事故の被害者の方にはわかりにくいことも多いと思います。
後遺障害認定の結果が届いたけれど、「併合」・「相当」・「加重」等の記載があり、「内容がよくわからない」、「適切な後遺障害等級が認定されているのかわからない」という方は、ぜひ一度弁護士に相談することをおすすめします。
交通事故に詳しい弁護士であれば、後遺症の内容・程度等に応じた適切な後遺障害等級が認定されているか否かを判断することができます。
また、通常、もっとも高額となる弁護士基準で賠償金額を算定し、被害者の方が適切な賠償金を受け取ることができるよう尽力します。
交通事故の被害はアディーレにご相談ください
交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。
弁護士費用特約を利用する方の場合は、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われます。
また、通常は弁護士費用が保険会社の上限額を超えた部分は自己負担となりますが、アディーレにご依頼いただく場合は、保険会社の上限を超えた分の弁護士費用は請求いたしません。
そのため、お手元からのお支払いはないため、安心してご依頼いただけます。
- ※弁護士費用特約の利用を希望する場合は、必ず事前に加入の保険会社にその旨ご連絡ください(弁護士費用特約には利用条件があります)。
【関連リンク】
弁護士費用特約が付いている場合の弁護士費用
弁護士費用特約が付いていない方でも、アディーレ独自の「損はさせない保証」により、保険会社提示額からの増加額より弁護士費用が高い場合は不足分の弁護士費用はいただかないことをお約束します。(※)
また、アディーレへのお支払いは獲得した賠償金からお支払いいただく「成功報酬制」です。(※)
お手元からのお支払いはないため、弁護士費用特約が付いていない方でも安心してご依頼いただけます。
- ※委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
【関連リンク】
弁護士費用特約が付いていない場合の弁護士費用
交通事故被害でお困りの方は、ぜひお気軽にアディーレ法律事務所にお問合せください。