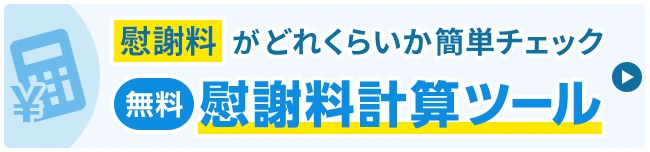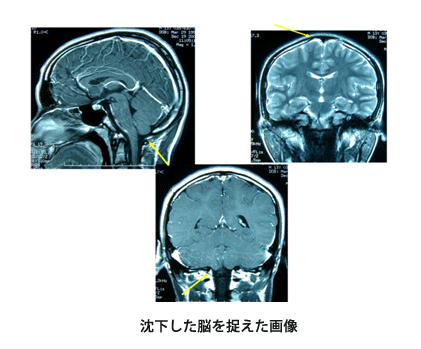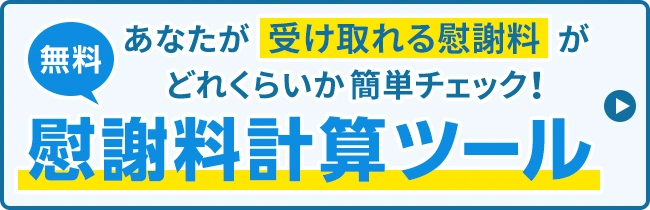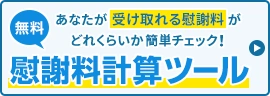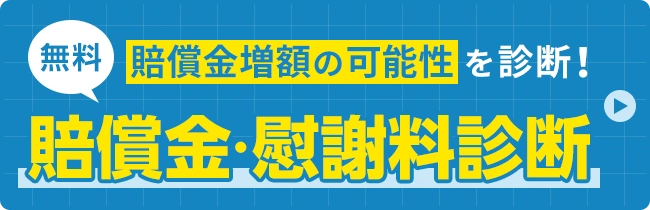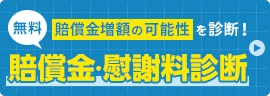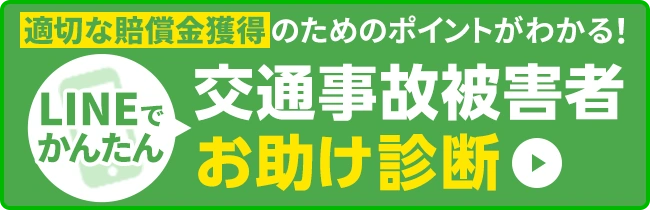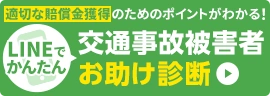- 目次
低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)とは
1.低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)とは
脳と脊髄はつながっており、脳から脊髄までを覆う閉鎖空間に浮いています。この脳と脊髄までつながる閉鎖空間を脳脊髄腔と呼びます。また、「浮いている」というのは、脳脊髄腔の中を満たす、脳脊髄液という液体の中に脳と脊髄が浮かんでいる、ということです。
- 画像提供 株式会社メディカルレビュー社
「脳脊髄液減少症ガイドライン2007」より
※画像の無断転載を禁ずる
症状は頭痛に限らず、そのほかにも、気分が悪くなり、吐き気がすることや、ひとつの物が2つに見えること、耳が聞こえにくいこと、首が痛いこと、視野が狭くなること、めまいなどが臨床症状として認められています。 その後、髄液圧が低下していないのに、同様の症状が現れている例が相当数あることがわかりました。そうして、次第に、上記症状は髄液圧の低下が必ずしも原因ではなく、髄液の漏出による髄液減少に原因があることがわかってきたのです。この見解に立つ医師らは、こうした病態を低髄液圧症候群と区別して、脳脊髄液減少症と位置づけています。
ところが、一般的には低髄液圧症候群および脳脊髄液減少症の両方が、並列的に使用されてしまっている状況があります。そこで、本文においては、以下とくにいずれかの意味に限定して用いる場合を除き、本傷病については低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)と表記することとします。
2.低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)とむち打ち損傷
この低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)が手術やケガなどを原因として生じることは早くから知られていました。手術によって脳脊髄腔に穴を開けてしまったり、尖ったものが背骨に刺さって脳脊髄腔に穴が開いてしまい、脳髄液が漏れ出してしまうことは比較的早期から知られていたのです。
これに対して、むち打ち損傷を原因として脳脊髄腔に穴があいて、脳脊髄液が漏れ出すことは、一般的に知られていませんでした。比較的軽微なむち打ち損傷等を契機として生じた類似の症状については、その発生原因が不明であることもあって、被害者の詐病ないしは心理的要因によるものだとされる傾向にありました。
しかし、近年、上記症状が、むち打ち損傷の慢性難治期(慢性期とは症状が激しい時期(急性期)をすぎて症状が一定程度で落ち着いてきた時期をいいます。慢性難治期とは、慢性期に残った症状が治りにくい状態を指しています)にみられるバレーリュー症候群の症状(むち打ち損傷を原因とする頭痛やめまい、吐き気、耳鳴り、難聴、動悸、声がかすれる、異常発汗、下痢など)と類似している点が着目されるようになりました。 そこで、むち打ち損傷の難治例(頭痛やめまいなどの症状が軽快しない場合)は低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)を原因とするものであるとの仮説が生まれました。その仮説のもと、上記症状を訴える患者に対し低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)の治療を行ったところ、それにより著明な改善があったとする医師らが現れました。低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)の治療というのは、硬膜外自家血注入等を指しています(硬膜外自家血注入に関しては、ワンポイントを参照ください)。
その結果、これまで原因不明だったむち打ち損傷に伴う症状が、低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)を原因とするものであるとの診断がなされるようになりました。そして、交通事故事件においても、むち打ち損傷等をきっかけとする低髄液圧症候群(脳脊髄液減少症)の発症が争われるようになっていったのです。
- 硬膜外自家血注入(Epidural Blood Patch:EBP)
-
一般的にブラッドパッチと呼ばれている治療法です。背骨の一番外側の膜を脊髄硬膜と呼びます。脊髄硬膜の内と外の間には、脂肪分を多く含んだ隙間があります。この隙間を脊髄硬膜外腔と呼びます。髄液が漏れている部分の脊髄硬膜外腔に、自家静脈血を注入して、髄液の漏れをふさぐのが硬膜外自家血注入と呼ばれる治療法です。
文章中に挿入した画像は、許諾を得て下記の書籍より転載しています。
改訂新版「脳脊髄液減少症ガイドライン2007」
株式会社メディカルレビュー社
画像の無断転載を禁じます