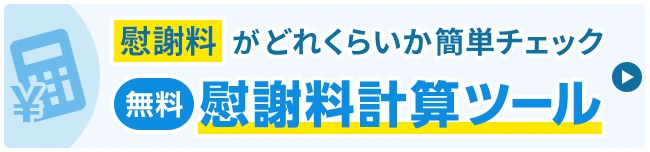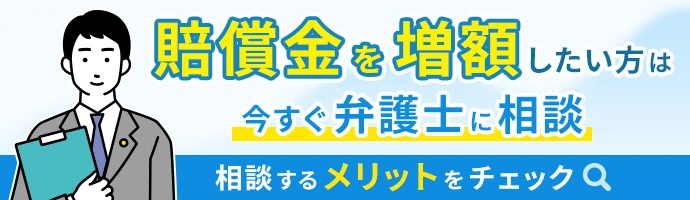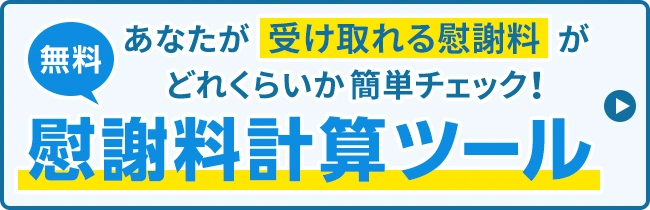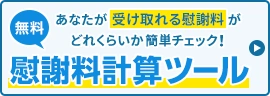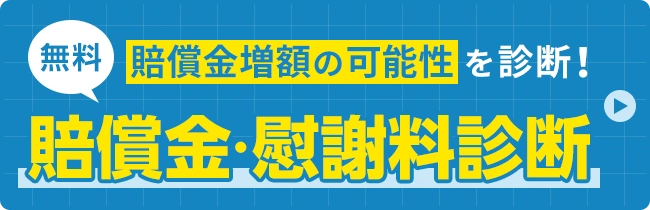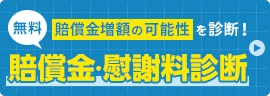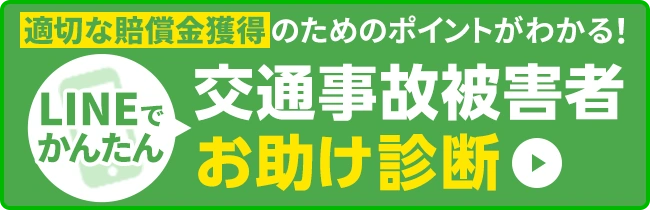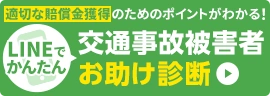後遺障害診断書を医師が書いてくれない!その理由と対処法

交通事故で負ったケガの治療を続けても症状が改善せず、何らかの症状が残ってしまった場合、「後遺障害」の認定を受けることが非常に重要です。
そして、適切な後遺障害等級の認定を受けるために不可欠なのが「後遺障害診断書」です。
しかし、「医師がなかなか書いてくれない」「書いてもらった内容が適切か不安」といった悩みを抱える方も少なくありません。
この記事では、後遺障害診断書の重要性から、医師が作成を渋る理由、そして医師に書いてもらえない・内容に不満がある場合の具体的な対処法について詳しく解説します。
- この記事でわかること
-
- 後遺障害診断書の重要性・作成方法
- 医師が後遺障害診断書を書いてくれない場合の理由と対処法
- 後遺障害診断書が必要になった場合に弁護士に依頼するメリット
- 目次
後遺障害診断書って何?基礎知識4つ
後遺障害診断書は、正式名称を「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」といい、事故によるケガを治療したにもかかわらず、完治せずに残ってしまった症状やその部位について記載した診断書です。では、この後遺障害診断書の基礎的な知識を確認しましょう。
後遺障害診断書はなぜ必要?
後遺障害診断書は、後遺障害認定を受ける際に必ず求められる重要な書面です。
後遺障害の等級認定を受けるためにはどのような後遺障害が残ったかを書面で証明する必要があります。
交通事故によるケガが、これ以上治療を続けても大幅な改善が見込めない状態(症状固定)と診断されたときには、医師に作成してもらいましょう。
後遺障害診断書は誰が書くの?
後遺障害診断書は、医師のみが作成できるものです。
たとえば、交通事故によるケガの治療で、整骨院に通うことがあると思います。しかし、整骨院の先生は柔道整復師であり、医師ではありません。そのため、柔道整復師に後遺障害診断書を作成してもらうことはできません。
交通事故にあってケガをした場合は、必ず早い段階で整形外科を受診して定期的に通院し、医師による継続的な診察を受けることが大切です。
後遺障害診断書の書式(雛形)は?
後遺障害診断書は、後遺障害に関連する内容を記載するものであり、決まった書式(雛形)があります。この雛形を入手するには、保険会社に雛形の送付を依頼したり、インターネットからダウンロードしたりする方法などがあります。
また、後遺障害が歯牙の障害の場合には、歯科用の後遺障害診断書が必要です。これは、交通事故により失われた歯がどれであるかなどを記入する書式です。
後遺障害診断書の作成費用はどれくらい?
後遺障害診断書の作成費用は各病院によって異なりますが、一般的には5,000円から1万円程度のところが多いようです。もちろんなかには、これより高い作成費用を設定している病院もあります。
作成費用の支払いは、被害者がいったん立て替えて、後遺障害等級が認定されてから相手方へ請求することが多いです。ただし、保険会社が一括対応している場合、保険会社が直接病院に支払うこともあります。
医師が後遺障害診断書を書いてくれない理由と対処法
交通事故で治療を続けても症状が残ってしまい、後遺障害の申請を考えたけれど、「医師が後遺障害診断書を書いてくれない」というケースがあります。
なぜ医師は作成を渋るのか、そしてそんなときにどう対処すべきか、よくあるケースとその解決策を具体的にご紹介します。
理由1「まだ症状固定の時期ではない」と判断している
後遺障害診断書は、「これ以上治療しても症状の改善が見込めない」という症状固定の診断があって初めて作成されるものです。
医師が「もう少し治療を続ければ、まだ回復の可能性がある」と考えている場合は、診断書の作成を時期尚早として断ることがあります。
対処法
まず、医師に症状固定の見込み時期を確認しましょう。
医師の判断に従って、見込み時期まで治療を継続することをおすすめします。
見込み時期が来たら、現在の症状を具体的に伝え、再度、後遺障害診断書の作成を依頼してみてください。
理由2「後遺障害がない」と考えている
被害者ご本人はつらい症状を訴えていても、医師が「治療の結果、もう完治した」「画像所見や検査結果からは、後遺症と判断できるものがない」と判断しているケースです。
また、なかには交通事故の後遺障害等級認定の基準に不案内だったり、診断書の書き方に不慣れだったりする医師もいます。
対処法
現在の症状を具体的に、詳しく医師に伝えましょう。
「いつ、どこが、どんなときに、どのように痛むのか」「そのせいで日常生活の何ができないのか」などを具体的に説明し、明確に伝わるよう工夫してください。
そのうえで、後遺障害診断書が賠償金請求のために非常に重要であることを丁寧に説明し、作成への協力を改めてお願いしてみましょう。
理由3「健康保険での治療だから診断書は書けない」と誤解している
ごく稀に、「健康保険を使って治療している患者さんの後遺障害診断書は書けない」と誤解している医師もいます。
しかし、交通事故の治療にも健康保険は利用できますし、健康保険を使っているからといって後遺障害等級書が書けない、ということはありません。
対処法
健康保険の利用と後遺障害診断書の作成は無関係であることを、医師に説明して誤解を解きましょう。
交通事故の治療に健康保険を利用することはまったく問題なく、健康保険を使って治療を受けていても後遺障害等級認定の申請は可能です。
この点を丁寧に説明し、改めて作成を依頼してみてください。
理由4「治療の経過を把握していないから書けない」(転院の場合)
事故後に病院を転院した場合、途中から診ることになった医師は、事故当初からの詳細な治療経過を把握していないため、「後遺障害診断書に必要な情報が足りない」と判断することがあります。
診断書には、事故当初の症状から現在の症状に至るまでの経緯や治療内容、回復状況などを詳細に記載する必要があるからです。
対処法
転院するまでの治療経過を記録した資料(紹介状、診断書、検査データなど)を前の医師から取り寄せ、現在診てもらっている医師に提示しましょう。
これらの資料をもとに、後遺障害診断書を作成してもらうよう依頼してください。
後遺障害診断書の書き直しが必要になったときは?
まず、後遺障害診断書を作成してもらったら、保険会社に提出する前にその内容を確認してみてください。
後遺障害診断書には、ご自身で自覚している症状やその原因となる他覚症状などを具体的かつ正確に記載してもらう必要があります。
もしも自分の言ったことが正確に伝わっておらず、記載が不十分である場合には、書き直しや修正をしてもらわなければなりません。
また、記入漏れがあったときには追記を依頼する必要があります。
対処法
後遺障害診断書の書き直しや追記ができるかどうかは、主治医の判断となりますが、応じてもらえるケースも多いようです。
後遺障害診断書は、自賠責調査事務所が後遺障害の有無や程度を判断するうえで、もっとも重視する資料です。特に痛みやしびれなどの神経症状は、診断書上の自覚症状の記載ごとに判断されるため、正しく等級認定を受けるためにはその記載内容が非常に重要となってくるのです。
そのほか、レントゲン、MRIなどの画像所見や、神経学的所見で有意な所見がある場合には、なるべくその所見について記載してもらうことが望ましいといえるでしょう。
交通事故被害の
無料相談は
アディーレへ!
後遺障害認定について弁護士に相談するメリット
後遺障害診断書は、あまり知識のない方が医師に作成を依頼した場合、不十分な内容の診断書になってしまい、適切な等級で認定を受けられない可能性があります。
かといって、ご紹介したような対処法を一般の方が満足に実践することは難しいでしょう。
そこで一つの解決策として、診断書作成の段階から「弁護士に依頼する」という方法があります。最後にそのメリットについて解説いたします。
後遺障害認定に必要な書類の準備をサポートしてくれる
後遺障害等級認定手続には、「事前認定」と「被害者請求」という2種類があります。
このうち被害者に有利なのは、「被害者請求」ですが、手続に非常に手間がかかります。
なぜなら後遺障害診断書以外にも、さまざまな書類を準備する必要があるためです。
保険金(損害賠償金額)支払請求書や交通事故証明書、診療報酬明細書、など…。これらの書類を一人で準備しようとすれば大変な労力が必要となります。
さらに、苦労してその書類を手に入れられたとしても、十分でなければ、必要な検査を追加ですべき場合もあります。
しかし、弁護士に依頼すれば、書類の内容の正誤や検査漏れの有無などをチェックし、必要なアドバイスをしてくれるため、必要書類の準備をする手間や漏れがなくなります。
医師との交渉もスムーズにできる
後遺障害診断書の作成を医師に断られた場合、代わりに弁護士が医師と交渉することで、診断書を作成してもらえることがあります。
また、診断書の書き直しや追記も弁護士が医師と交渉することで、よりスムーズに進むことが多いです。
弁護士費用特約があれば費用を気にせず依頼できる
ご自身が加入されている自動車保険などに弁護士費用特約が付いている方は、発生する弁護士費用を保険会社が負担してくれるため、費用を気にせずにご依頼いただけます。 ご自身が加入している保険をぜひ確認してみてください。
弁護士費用特約が付いていない方でも、アディーレ法律事務所なら、独自の「損はさせない保証」により、保険会社提示額からの増加額より弁護士費用が高い場合は不足分の弁護士費用はいただきません。(※)
また、アディーレの交通事故被害に関する弁護士費用は、獲得した賠償金からお支払いいただく「成功報酬制」。(※)お手元からのお支払いはないため、弁護士費用特約が付いていない方でも安心してご依頼いただけます。
- ※委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いただきます。
まとめ
上記で見たこと以外にも、後遺障害診断書の作成を断られるケースはいろいろと考えられます。そのような場合にも、それぞれの状況に応じて適切に対応する必要があります。もし適切な対応ができなければ、誤った等級認定を受けるおそれがあります。
被害者の方ご自身だけでそのすべてに対応するのはご負担が大きいでしょう。
そこで、交通事故事件の解決実績が豊富な弁護士を探し、依頼すれば、適切に対処してくれます。「後遺障害診断書にどのようなことを記載すべきか」という点を、一般の方が理解するのは難しいと言わざるを得ません。
したがって、後遺障害診断書の作成に困った場合には、まずは弁護士へのご相談をおすすめいたします。