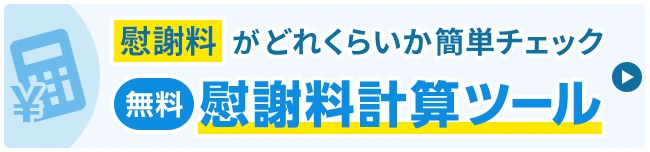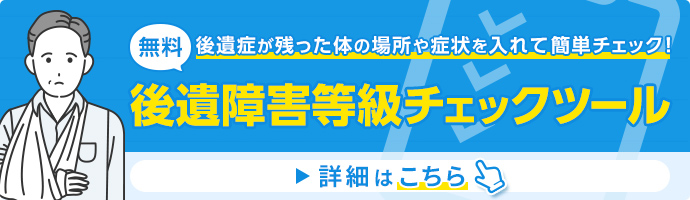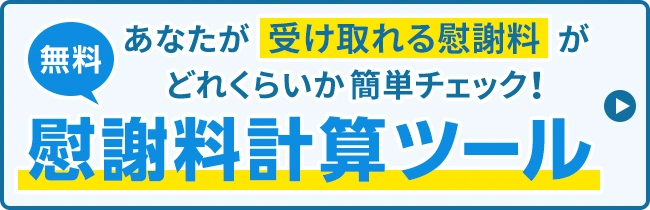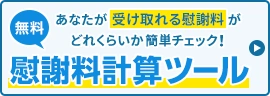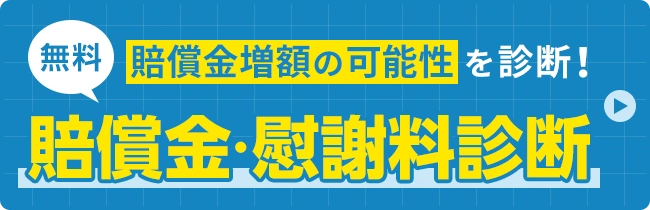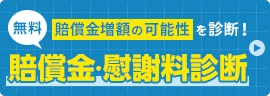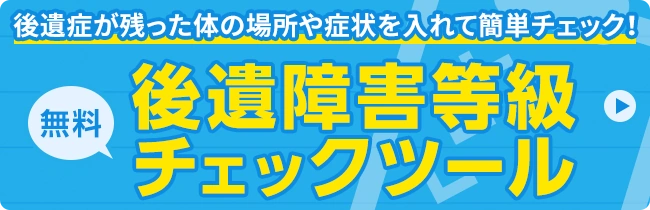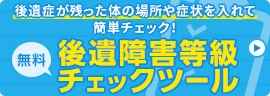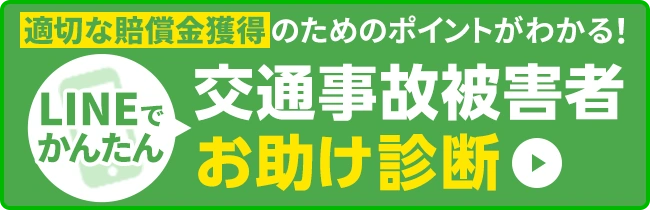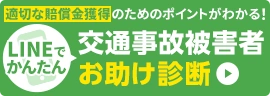腰椎圧迫骨折で認められる後遺障害等級と慰謝料について

自転車やバイクで交通事故にあい、転倒して腰部を強く打ちつけたり、高速度で追突されたりした場合に、腰椎圧迫骨折が生じる場合があります。
腰椎圧迫骨折の症状としては、痛みやしびれが残り日常生活に大きな支障が生じてしまう、骨が変形してしまうなどがあり、後遺症につながることも珍しくありません。
そこで本コラムでは、腰椎圧迫骨折が発生した場合、どのような後遺障害が認められるのか、受け取れる慰謝料はいくらなのかなどについて解説していきます。
- この記事でわかること
-
- 腰椎圧迫骨折の症状
- 腰椎圧迫骨折で認められる後遺障害の種類
- 腰椎圧迫骨折で請求できる後遺症慰謝料の相場
- 目次
交通事故被害の
無料相談は
アディーレへ!
腰椎圧迫骨折とは
腰椎とは、上下に連なる背骨のうち、頸椎・胸椎の下に続く5個の骨のことをいいます。簡単に言えば、背骨の下のほうにある骨のことです。
この腰椎に圧力がかかってつぶれたように骨折した状態を、「腰椎圧迫骨折」といいます。
また、腰椎が破裂するように、複数の骨が広い範囲で骨折した状態を「腰椎破裂骨折」といいます。
腰椎圧迫骨折の症状
交通事故による腰椎圧迫骨折は、骨折部分の痛みが主な症状として発生します。
骨折の程度によって痛みに個人差はありますが、体の中心に位置する腰は、あらゆる動作を支える基盤となるため、起き上がったり、立ち上がったりするときに強い痛みが生じることも多いのです。
また、痛み以外にも、下肢のしびれや麻痺等の症状が出る可能性も考えられます。
腰椎圧迫骨折の後遺障害等級
後遺障害とは、交通事故でケガを負ったあと、十分な治療をしたにもかかわらず、後遺症が残ってしまった場合にその症状の重さによって1~14の等級に分類したものです。
腰椎圧迫骨折による代表的な後遺障害として、「変形障害」と「運動障害」の2つがあります。それぞれの障害について、詳しく見ていきましょう。
変形障害(腰椎が変形した)
変形障害としては、以下の後遺障害等級が認められる可能性があります。
- 6級5号(脊柱に著しい変形を残すもの)
- 8級相当(脊柱に中程度の変形を残すもの)
- 11級7号(脊柱に変形を残すもの)
脊椎圧迫骨折等が生じており、骨折の状態がX線写真等により確認できれば、少なくとも11級7号に認定されます。
もっとも、圧迫骨折であっても、椎体(脊椎を形成するリング状の部分)のヒビのみにとどまり、変形が軽微であるとして、変形が認められないこともあります。
そのため、たとえ圧迫骨折という診断であっても、X線写真等で変形の程度を確認する必要があるでしょう。
また、事故直後の変形が小さくても、日常生活のなかで蓄積された負担などにより、数ヵ月かけて椎体の変形が進行するケースもあります。
特に高齢者の場合は、若年者と比べて骨組織が弱くなっていることも多く、事故にあってケガをしてから、3ヵ月程度経過したあとに、再度X線写真を撮影することが好ましいです。
そのため、当初医師から「骨に異常なし」と診断されたとしても、痛みが継続するようであれば、椎体の変形が進行している可能性もあるので、再度撮影を行うべきでしょう。
なお、高齢者の場合、X線写真上では、加齢性の変形が圧迫骨折のように見えることもあり、交通事故と圧迫骨折との因果関係が問題になることもあります。
通常、圧迫骨折は、歩行者対自動車の事故や、二輪車の衝突・転倒事故、追突速度が時速60キロ以上の激しい追突事故といった、大きな交通事故で発症するものです。
そのため、因果関係が問題になった場合には、「圧迫骨折が生じうるほどの交通事故であったのか」、「事故直後の新鮮な圧迫骨折による強い痛みや炎症があったのか」などを加味して、因果関係の有無について判断していくことになります。
運動障害(腰が動かしにくい)
運動障害としては、以下の後遺障害等級が認められる可能性があります。
- 6級5号(脊柱に著しい運動障害を残すもの)
- 8級2号(脊柱に運動障害を残すもの)
厚生労働省が定める具体的な認定基準は、下記のとおりです。
6級5号
次のいずれかにより頸部および胸腰部が強直したもの
ア‐頸椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎圧迫骨折が存しており、そのことがX線写真等により確認できるもの
イ‐頸椎および胸腰椎のそれぞれに脊椎固定術が行われたもの
ウ‐項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
8級2号
ア‐次のいずれかにより、頸部または胸腰部の可動域が参考可動域角度の1/2以下に制限されたもの
a.頸椎または胸腰椎に脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがX線写真等により確認できるもの
b.頚椎または胸腰椎に脊椎固定術が行われたもの
c.項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
イ‐頭蓋・上位頸椎間に著しい異常可動性が生じたもの
神経症状(痛みやしびれが残った)
神経症状としては、以下の後遺障害等級が認められる可能性があります。
- 12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)
- 14級9号(局部に神経症状を残すもの)
12級13号は、局部に頑固な神経症状(痛みやしびれなど)を残すもののうち、障害の存在が医学的に説明可能なものを指します。
詳しく説明すると、MRIやレントゲン、CTなどの画像診断で神経の圧迫が認められ(=他覚的所見あり)、医学的な検査で神経の圧迫と症状の関連が確認できるものです。
14級9号は、痛み・しびれなどの自覚症状があっても、MRIやレントゲン、CTなどの画像診断で神経圧迫が確認できない場合(他覚的所見なし)や、医学的な検査で神経の圧迫と症状の関連が確認できない場合に認定される余地があります。
腰椎圧迫骨折の後遺障害慰謝料の相場
後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料を獲得することができます。
これは、“後遺障害が残ってしまったことに対する精神的損害の賠償”として支払われるものですが、この金額は自賠責保険から支払われる金額(自賠責保険基準)と弁護士に依頼した場合に支払われる可能性のある金額(弁護士基準)とで大きく差があります。そのため、損をしないためには弁護士に依頼して交渉するほうがよいといえるでしょう。
一例として、これまでに紹介した以下の等級における賠償金額を比較してみます。
| 後遺障害等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 第6級 | 512万円 (498万円) | 1,180万円 |
| 第8級 | 331万円 (324万円) | 830万円 |
| 第11級 | 136万円 (135万円) | 420万円 |
- ※()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合
また、後遺障害等級の認定によって、逸失利益(交通事故による後遺症がなければ、将来得られたはずの収入)も認められます。
もっとも、変形障害11級においては、骨が多少変形しても労働能力は失われず、保険会社が逸失利益を提示してこないケースもあるため、注意が必要です。
11級でも痛みが残ることは多く、慢性的な痛みが生じている場合、たとえ体をあまり動かさない事務職であったとしても、集中力の欠如から労働能力に影響をおよぼすことも考えられます。
保険会社に対して、主張するべきところはしっかりと主張していきましょう。
交通事故被害の
無料相談は
アディーレへ!
腰椎圧迫骨折で適切な賠償金を受け取るためのポイント
適切な賠償金を受け取るために覚えておきたいポイントをご紹介します。
弁護士基準で慰謝料を算定する
同じ後遺障害等級でも、採用する基準で慰謝料額が大きく変わってきます。
保険会社は自賠責保険基準もしくは独自の基準で算定した金額を提示してくることが多く、裁判をしたならば認められる弁護士基準(裁判所基準)で請求することにより、最終的な賠償金を増額できる可能性が高いです。
そのため、すぐに示談せず、交通事故に詳しい弁護士に一度相談されることをおすすめします。
適切な後遺障害等級の認定を受ける
後遺障害の等級に応じて、後遺障害慰謝料や逸失利益の金額が変わってくるため適切な後遺障害等級認定を受けることが大切です。
もし、腰椎圧迫骨折以外のケガの後遺障害が認められた場合、腰椎圧迫骨折の等級と併合されて等級が上がることもあります。
認定結果に納得がいかない場合、異議申立てをすることも可能です。
しかし、後遺障害等級認定の申請手続はさまざまな資料を必要とします。
また、資料に不足がないかどうかの判断には、法律的・医学的な専門知識も必要です。
そこで弁護士に依頼し、申請のサポートを受けることで適切な後遺障害等級認定の獲得を目指せます。
まとめ
交通事故による腰椎圧迫骨折の後遺障害等級は、適切な認定を受けるためのコツがあります。
また、交通事故の示談交渉は、通常、事故の相手方(加害者)が加入する保険会社と行うことになりますが、保険会社は交渉のプロであり、プロを相手に、被害者自身で交渉を行うのは容易ではないのが実情です。
後遺障害等級の認定手続や示談交渉を弁護士に依頼すれば、適切な等級認定を受けられる可能性や慰謝料金額を増額できる可能性が高まります。
交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
交通事故の被害はアディーレにご相談ください
交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。
弁護士費用特約を利用する方の場合は、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われます。
また、通常は弁護士費用が保険会社の上限額を超えた部分は自己負担となりますが、アディーレにご依頼いただく場合は、保険会社の上限を超えた分の弁護士費用は請求いたしません。
そのため、お手元からのお支払いはないため、安心してご依頼いただけます。
- ※弁護士費用特約の利用を希望する場合は、必ず事前に加入の保険会社にその旨ご連絡ください(弁護士費用特約には利用条件があります)。
【関連リンク】
弁護士費用特約が付いている場合の弁護士費用
弁護士費用特約が付いていない方でも、アディーレ独自の「損はさせない保証」により、保険会社提示額からの増加額より弁護士費用が高い場合は不足分の弁護士費用はいただかないことをお約束します。(※)
また、アディーレへのお支払いは獲得した賠償金からお支払いいただく「成功報酬制」です。(※)
お手元からのお支払いはないため、弁護士費用特約が付いていない方でも安心してご依頼いただけます。
- ※委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
【関連リンク】
弁護士費用特約が付いていない場合の弁護士費用
交通事故被害でお困りの方は、ぜひお気軽にアディーレ法律事務所にお問合せください。