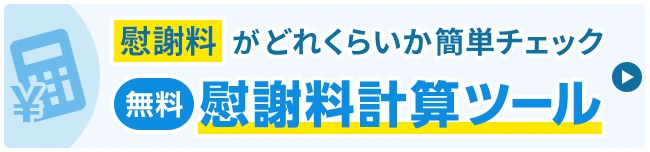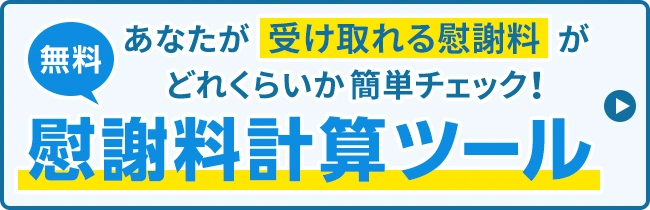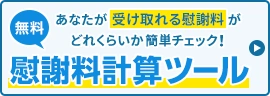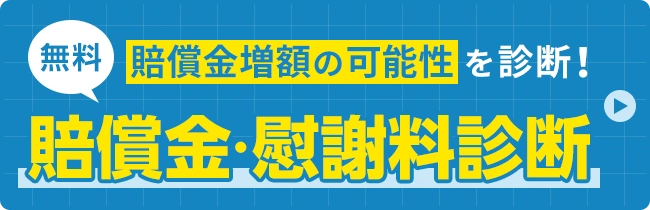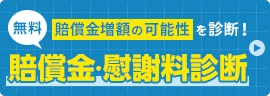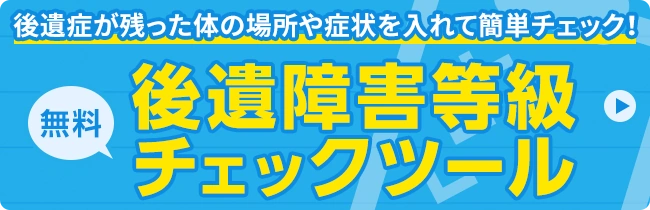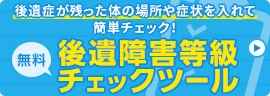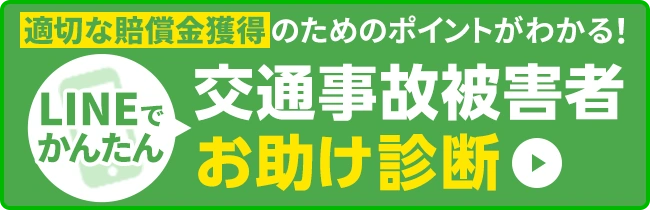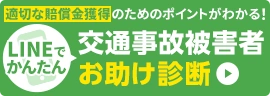交通事故で遷延性意識障害になったら?後遺障害や損害賠償請求について解説

遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)は、交通事故による頭部外傷などによって、意思疎通や移動がまったくできない寝たきりの状態が長期間続くことを指します。しばしば、「植物状態」などとも呼ばれます。
事故にあわれた被害者の方はもちろん、ご家族の方々も精神的・肉体的・経済的な負担を強いられることになります。
ですから、そのようなご負担を少しでも軽くするために、適切な賠償金を受け取ることは非常に大切です。
この記事では、交通事故の被害にあわれた方や被害者を支える
ご家族の方のご負担を軽減できるよう、遷延性意識障害の後遺障害等級や損害賠償請求について詳しく解説いたします。
- この記事でわかること
-
- 遷延性意識障害の原因・症状・治療法
- 遷延性意識障害の後遺障害認定のポイント
- 請求できる損害賠償金と請求の流れ
- 目次
交通事故被害の
無料相談は
アディーレへ!
交通事故における遷延性意識障害とは?
交通事故における遷延性意識障害とは、交通事故被害のなかでもっとも重い後遺障害です。
一般的には植物状態と呼ばれている、移動や意思疎通、排せつなどがご自身でできない、寝たきりの状態になることをいいます。
ここでは、遷延性意識障害となる原因や症状、治療法などについて解説します。
遷延性意識障害の原因
歩行者が自動車に衝突された場合、歩行者は道路に投げ出されて頭部に外傷を受けやすいことは容易に想像できると思います。
このように交通事故による頭部外傷などによって、脳に何らかの重い障害が残り、昏睡状態になったあと、意思疎通がまったくできない長期の意識障害「遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)」になってしまうことがあります。
遷延性意識障害の症状
遷延性意識障害は、遷延性植物状態と表記されることもあります。いわゆる植物状態です。
植物状態は、以下の6項目を満たす状況に陥り、治療をしたにもかかわらず改善が見られず3ヵ月以上が経過したものと定義されています(日本脳神経外科学会より)。
- 自力移動ができない
- 自力摂食ができない
- 糞尿失禁状態にある
- 意味のある発語ができない
- 簡単な命令にはかろうじて応じることもあるが、意思疎通はほとんどできない
- 眼球は動いていても物を認識することはできない
つまり、寝たきりで、自分では体を動かすことも言葉を発することもできない状態をいいます。
遷延性意識障害の治療法と回復の可能性
遷延性意識障害は、脳機能の停止状態である「脳死」とは異なり、脳幹機能は正常で自力で呼吸もできます。
ただ、これに対する有効な治療方法は、今のところ確立されていません。治療方法として、脊髄電気刺激法や脳深部電気刺激法などがありますが、回復可能性が高いとはいえません。
したがって、患者自身の自然治癒力による回復を待つ必要があります。
回復を待つ間は、寝たきりのため、関節が固まり動かなくなってしまわないよう関節拘縮の予防や、床ずれ防止のために体位交換、排せつ処理、痰の吸引など、常時の介護が必要になります。
遷延性意識障害で認められる後遺障害等級
治療をしてもこれ以上よくならない状態になったとして「症状固定」と判断される場合があります。
症状固定と判断された場合には、症状の程度などによって、後遺障害の申請をするかどうか検討することになります。
後遺障害は、症状の内容や程度などにより、1級から14級までの等級に分けられ、1級が一番重い等級として規定されています。
【関連コラム】
交通事故の症状固定とは?ベストタイミングとその後の対応を解説
「遷延性意識障害」の後遺障害等級としては多くの場合、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」にあたり、後遺障害1級が認定されることになります。
遷延性意識障害の後遺障害慰謝料の相場
後遺障害慰謝料とは、後遺症に伴う精神的な苦痛に対する賠償金です。
後遺障害慰謝料は、後遺障害の等級ごとに金額が規定されています。
慰謝料には3つの基準がある
慰謝料の計算を行う際には、以下の3つの基準があります。
- 自賠責保険基準
- 任意保険基準
- 弁護士基準(裁判所基準)
自賠責保険基準は、自賠責保険の支払いの基準です。自賠責保険は被害者救済のため最低限の補償をするものなので、3つの基準のなかでは通常もっとも低額となります。
任意保険基準は、各任意保険会社が独自に定める基準です。任意保険基準は、一般には公表されていません。
弁護士基準(裁判所基準)は、過去の裁判例をもとに設定されている基準です。弁護士基準は、3つの基準のなかで通常もっとも高額となります。
| 後遺障害等級 | 自賠責保険基準 | 弁護士基準 |
|---|---|---|
| 1級(別表1) | 1,650万円(1,600万円) | 2,800万円 |
- ※()内は2020年3月31日以前に発生した事故の場合
なお、自賠責保険基準による慰謝料額については、1級(別表1)が認定されると、初期費用等として500万円が増額されます。また、被扶養者がいるときには1,650万円から1,850万円に増額されます。
そのため、被扶養者のいる被害者の方が遷延性意識障害と認定された場合の慰謝料額は2,350万円となります。
このように、慰謝料の算定基準によって金額が大きく変わってきます。
そのため、適切な後遺障害慰謝料を得るためには弁護士基準で算出することが重要です。
遷延性意識障害と認定された場合に請求できる可能性のある賠償金
遷延性意識障害の場合に、後遺障害慰謝料以外にも加害者に請求できる可能性のある賠償金は下記のとおりです。
症状固定までに生じる損害
- 治療費
- 入通院交通費
- 付添看護費
- 入通院慰謝料
- 入院雑費
- 器具購入費
など
症状固定後の後遺障害による損害
- 逸失利益
- 近親者慰謝料
遷延性意識障害の場合に損害として認められる可能性のある損害
さらに、遷延性意識障害の場合には、上記に加えて、下記の項目も損害として認められる場合があります。
- 将来の介護費
- 将来雑費(おむつや介護ベッドなどの介護用品の費用)
- 成年後見人選任の申立費用
など
損害賠償を請求する流れ
損害賠償を請求するまでの大まかな流れは、以下のとおりです。
- 入院・治療
- 症状固定
- 後遺障害の申請・認定
- 賠償金の請求・交渉
遷延性意識障害を負うような大きな事故の場合、通常は入院して治療を行います。
そして、医師の判断をもとに症状固定を迎えます。
後遺障害等級認定の申請をし、等級が認定されたら賠償金の請求をして金額などの交渉をしていくことになります。
成年後見人の選任が必要な場合がある
交通事故が原因で遷延性意識障害になってしまった場合、加害者に対して損害賠償請求をすることができます。
本来、賠償金請求は被害者本人が行うのが原則ですが、交通事故被害者が寝たきりで意思疎通をはかることが難しい場合、原則「成年後見人」の選任が必要です(※)。
成年後見人とは、認知症、知的障害、精神障害、病気などによって大体において判断能力を喪失している人を保護する制度です。
「成年後見人」であれば被害者に代わって、加害者に対して損害賠償請求をすることがすることが可能です。
なお、「成年後見人」制度を利用するためには家庭裁判所による選任が必要であり、「成年後見人」の選任には家庭裁判所に成年後見人の選任の申立てを行うことが必要です。
- ※被害者が未成年者の場合は、親権者(父母)が法定代理人として、賠償金請求などを行うことができます(成年後見人の選任は不要)。
遷延性意識障害の場合の損害賠償請求は弁護士に任せるのがおすすめ
遷延性意識障害は賠償項目が多く、また後遺障害等級も1級と高いため、通常は賠償額が極めて高額となります。
そのため、加害者側との交渉においてもめる可能性が高いといえます。
遷延性意識障害おける損害賠償請求を弁護士に依頼する主なメリットは下記のとおりです。
1.不利な過失割合になっていないかチェックする
保険会社の提示する過失割合は、被害者の主張ではなく、加害者の主張する事実に基づいて過失割合を提案してきている可能性があり、被害者に不利な形になっているケースもあり得ます。
弁護士であれば、被害者の証言はもちろん、警察の捜査資料(目撃者の証言や防犯カメラ映像などを含む)などを精査して、被害者にとって不利な過失割合になっていないかを確認し、適切な過失割合を主張することができます。
2.賠償金の項目に漏れがないかをチェックする
遷延性意識障害の賠償項目は多岐にわたるため、すべての項目を適切な金額で請求できているかを把握するのは難しいものです。
適切な賠償金を受け取れるよう、賠償金の項目がすべてにおいて適切な金額になっているかを確認し、不足している項目についてはきちんと支払うよう主張していきます。
3.複雑な手続を任せることができる
被害者が植物状態になった場合、被害者のご家族の精神的・肉体的・金銭的な負担はとても大きいものでしょう。
弁護士に依頼することで、後見人選任手続や賠償金請求に関する手続を任せられるため、さまざまな負担を軽減することができます。
加えて、保険会社からの主張への反論などもしてもらうことが可能なため、結果として、適切な賠償金を受け取れる可能性につながりが高まります。
【関連リンク】
遷延性意識障害(植物状態)の後遺障害等級認定と賠償金
交通事故で遷延性意識障害と診断されたら弁護士に相談
遷延性意識障害と診断された被害者の方の介護をしていくことは、それだけでもご家族にとって大きな負担となります。
成年後見申立手続の準備や、保険会社が提案してきた金額が妥当であるかの判断などを行うことは難しいでしょう。
少しでもご負担を軽減し、適切な賠償金が得られるよう、まずは信頼できる弁護士に相談されることをおすすめいたします。
交通事故の被害はアディーレにご相談ください
交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。
弁護士費用特約が付いていない方は、アディーレ独自の「損はさせない保証」により、保険会社提示額からの増加額より弁護士費用が高い場合は不足分の弁護士費用はいただかないことをお約束します。(※)
また、アディーレへのお支払いは獲得した賠償金からお支払いいただく「成功報酬制」です。(※)お手元からのお支払いはないため、弁護士費用特約が付いていない方でも安心してご依頼いただけます。
- ※委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
【関連リンク】
弁護士費用特約が付いていない場合の弁護士費用
弁護士費用特約を利用する方の場合は、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはり相談者の方・依頼者の方に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。
なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。
また、通常、弁護士費用がこの上限額を超えた部分は自己負担となりますが、アディーレにご依頼いただく場合は、保険会社の上限を超えた分の弁護士費用は請求いたしません。
お手元からのお支払いはないため、安心してご依頼いただけます。
- ※弁護士費用特約の利用を希望する場合は、必ず事前に加入の保険会社にその旨ご連絡ください(弁護士費用特約には利用条件があります)。
【関連リンク】
弁護士費用特約が付いている場合の弁護士費用