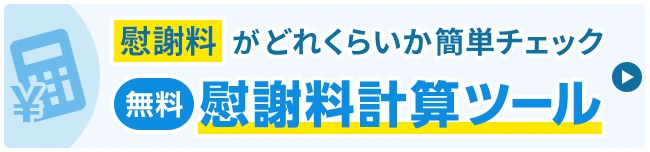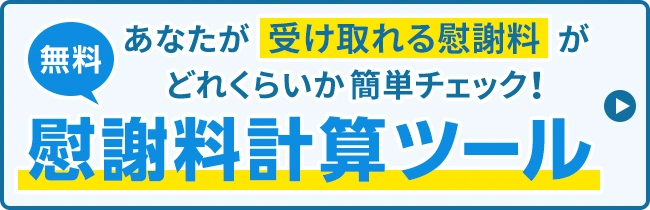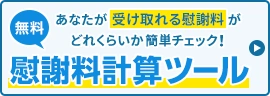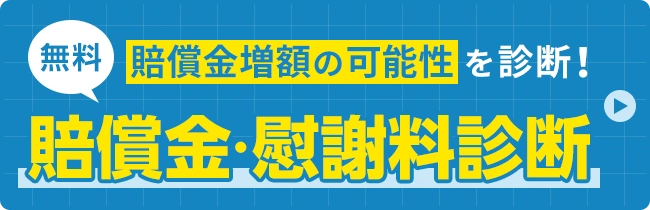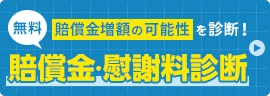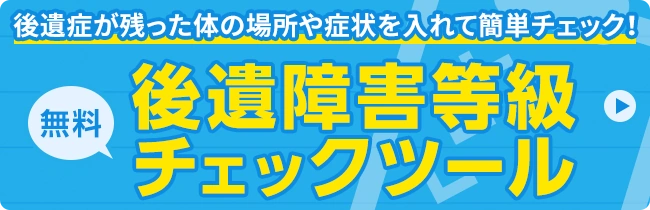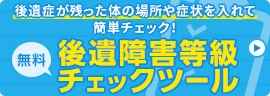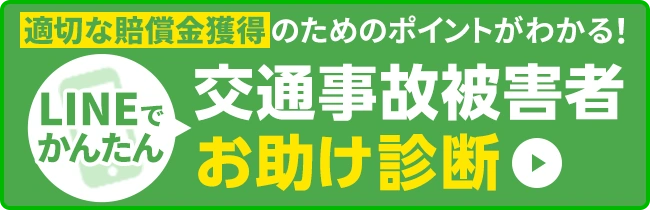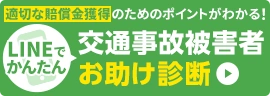交通事故の休業損害の計算方法は?いつ受け取れる?請求方法や対象者、注意点なども解説

「休業損害」とは、交通事故の賠償金の項目の一つで、事故によるケガで仕事ができなかったために失った収入を補償するものです。
給与所得者、自営業者、家事従事者など働き方によって計算方法が異なります。
突然の交通事故で収入を絶たれた被害者の方にとって、適切な休業損害を得ることは大切です。
このコラムでは、休業損害の概要や計算方法、適切な休業損害を受け取るために知っておくべきことなどについて解説します。
- この記事でわかること
-
- 休業損害の概要と計算方法
- 休業損害の請求方法と支払い
- 休業損害を請求する際の注意点
- 目次
交通事故被害の
無料相談は
アディーレへ!
交通事故における休業損害とは
「休業損害」とは、加害者側に請求する交通事故の賠償金の項目の一つです。交通事故によるケガが原因で仕事を休んだ結果、減ってしまった収入を補填するために支払われます。
慰謝料や休業補償との違い
慰謝料とは
交通事故の慰謝料は、交通事故によって受けた精神的・身体的な苦痛や損害に対し、加害者側から支払われるお金のことです。
休業損害が経済的な損失に対する補償であるのに対し、慰謝料は精神的・身体的な損害に対する補償であるという違いがあります。
交通事故における慰謝料について詳しく知りたい方は、下記コラムをご覧ください。
休業補償とは
休業補償は、通勤中や勤務中の交通事故によるケガで仕事を休み、収入が減った場合の補償として、労災保険から支払ってもらえるお金のことです。
これに対して、休業損害は交通事故の加害者側から支払われる「損害賠償金」であり、請求先や対象となる交通事故などに違いがあります。
ただし、休業補償と休業損害の両方を受け取ることはできません。
休業補償と休業損害との違いについて詳しく知りたい方は、下記コラムをご覧ください。
【関連コラム】
交通事故の休業補償とは?もらえる条件・金額・期間を解説
休業損害が認められないケース
交通事故でケガをしたからといって、休業損害が必ず認められるとは限りません。
たとえば、下記のようなケースでは、休業損害を認めてもらえない場合があります。
年金や生活保護の受給者の方
年金や生活保護の受給者の方は、交通事故でケガをしたとしても受け取れる年金や生活保護費の額が減ることはありませんから、休業損害を請求することはできないといえます。
不労所得だけで生活をしている方
家賃収入や株式の配当金のみといった不労所得のある方は、交通事故でケガをしたとしても収入が減らないため、休業損害は発生しないと判断される場合が多いです。
ただし、交通事故で契約書の取り交わしができず、賃貸契約が延期となってしまった場合など、収入が減ったことが認められれば、休業損害を請求することができます。
休業損害の基本的な計算方法
休業損害は「日額賃金 × 休業日数」で計算されます。この日額賃金は、被害者の職業や収入状況によって異なります。
日額賃金の算定方法
日額賃金の算定については、「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」の3つの基準があります。
| 算定基準 | 日額賃金の求め方 |
|---|---|
| 自賠責保険基準 | 原則6,100円(※) 上限1万9,000円 (1日の休業損害が6,100円を超えると証明できる場合は日額19,000円を上限に増額できる場合あり) |
| 任意保険基準 | 自賠責保険基準とほぼ同額もしくはやや高い程度 |
| 弁護士基準 | 交通事故前3ヵ月間の被害者の収入を日割りにした金額 |
- ※令和2年3月31日以前に発生した事故の日額は5,700円
通常、弁護士基準によって算定した日額賃金がもっとも高額となりますが、加害者側の保険会社が提示してくる金額は、自賠責保険基準や任意保険基準で算定したものが多いです。
あらかじめ適切な日額賃金を算定したうえで、保険会社との交渉に臨むことをおすすめします。
休業日数の数え方
休業日数は、基本的に治療開始から完治または症状固定までの間の、治療のための入院・通院で仕事を休んだ日数です。
完治または症状固定までに行ったリハビリのための休業についても、原則として認められます。
【被害者の職業別】休業損害の計算方法
休業損害は、給与所得者や自営業者などに加えて、専業主婦(主夫)も請求できます。また、学生や無職者も休業損害の対象となるケースがあります。
休業損害の計算方法は職業によって異なります。それぞれ確認していきましょう。
【休業損害の対象となる可能性のある方】
- 給与所得者(パート・アルバイトを含む)
- 自営業者・個人事業主
- 会社役員
- 専業主婦(主夫)
- 無職・失業中
- 学生
①給与所得者(パート・アルバイトを含む)
過去の給与(基本給に家族手当などの各種手当も加算した総支給額)をもとに算出した日額賃金に休業日数をかけて計算します。
【給与所得者の休業損害】
(事故前3ヵ月分の給与額÷稼働日数)×休業日数
なお、賞与の減少や住宅手当などの各種手当の減少、昇給の遅れといったことが起きた場合、交通事故との関連性を証明できれば休業損害として請求することが可能です。
②自営業者・個人事業主
過去の確定申告書や収入帳簿をもとに算出した日額賃金に休業日数をかけて計算します。年度間で収入の変動がある場合、事故前数年分の平均額を用いることが一般的です。
【自営業者・個人事業主の休業損害】
(事故前年の確定申告所得額÷365日)×休業日数
③会社役員
会社役員の役員報酬は「利益配当分」と「労働対価分」に分けられます。
このうち、労働がなくても支給される「利益配当」に該当する部分を除いた「労働対価分」に相当する金額のみを日額賃金とし、これに休業日数をかけて計算します。
【会社役員の休業損害】
{(役員報酬-利益配当分)÷365日}×休業日数
たとえば、社外取締役や社外監査役などが受け取る役員報酬は利益配当分が多くを占めていることから、休業損害が認められない可能性があります。
小規模会社や家族経営の役員等で、労働対価分が多くを占めている場合は、休業損害が認められる可能性があります。
④家事従事者(専業主婦・専業主夫)
家事従事者は、家事労働をしても給料を受け取ることがないため、休業損害が発生しないように思えるかもしれません。
しかしながら、裁判において、家事労働は金銭的に評価すべきであると判断されています。
専業主婦(主夫)の場合、賃金センサスの全年齢女子平均年収をもとに算出した日額賃金に休業日数をかけて計算します。
【家事従事者の休業損害】
(賃金センサスの女子全年齢平均年収(※)÷365日)×休業日数
- ※令和元年に起きた事故の場合、令和元年賃金センサスを参照に女性の平均年収額388万100円を基準に計算します。
なお、家事労働をしながらお仕事をされている兼業主婦(主夫)の方については、年収額により給与所得者と判断される場合があります。
家事従事者の休業損害について詳しく知りたい方は、下記コラムをご覧ください。
⑤無職・失業中
無職・失業中の方はそもそも事故により仕事を休むということがないため、原則として休業損害が認められません。休業損害を認めてもらうには、下記の条件を満たしている必要があります。
- 被害者の方に就労の意思があった
ハローワークに通って再就職先を探していたなど、労働意欲が高かった場合 - 被害者の方に就労の能力があった
心身ともに健康で就労に支障がない、特定の資格や専門技能を持っているなど、労働能力がある場合 - 被害者の方に就労の可能性があった
事故前にすでに内定を得ており、交通事故がなければ働いていた可能性が高い場合
上記に当てはまる無職や失業中の方の休業損害は、賃金センサスや失業前の収入などを参考に、算定した日額賃金に休業日数をかけて計算します。
【無職・失業中の休業損害】
<内定が出ていた場合>
(賃金センサスまたは就職予定先の推定年収額÷365日)×休業日数
<内定は出ていないが就労の可能性が高い場合>
(賃金センサスまたは失業前の収入額÷365日)×休業日数
⑥学生
学生で収入がない場合は原則として休業損害が認められません。ただし、下記のような状況にある学生は、休業損害を請求できる可能性があります。
- アルバイトによる収入があった
- 事故による内定取り消しや留年により就職時期が遅れた
【学生の休業損害】
<アルバイト収入のある学生>
{事故前3ヵ月の給与合計額÷稼働日数(出勤日数)}×休業日数
<内定が出ていた場合>
(就職予定先の推定年収額÷365日)×休業日数
<内定は出ていないが就労の可能性が高い場合>
(賃金センサスの平均賃金(年収)÷365日)×休業日数
交通事故が原因で退職した場合
交通事故によるケガや後遺障害が原因で退職した場合でも、休業損害を請求できることがあります。
ただし、「交通事故のせいで退職した」と証明することが必要です。ポイントとしては、下記のようなものが挙げられます。
- 交通事故によるケガの程度:寝たきりや歩行困難などで就業が困難な状態である、など
- 仕事の内容:身体を使う仕事である、など
- 退職の理由:会社都合の退職である(自主退職の場合は認められにくい)
- 再就職の可能性:再就職が困難なケガである
有給休暇を取得した場合
入院・通院で仕事を休む際に有給休暇を使用した場合も、休業損害を受け取ることができます。
ただし、有給休暇の取得について、すべてが休業損害として認められるとは限らないため、注意が必要です。
①有休ではなく代休を使って通院した
有休ではなく代休を使って通院した場合、休業損害は認められないのが通常です。
代休は休日出勤の代わりにほかの就業日に休むという制度です。
「会社の休日に通院した」と判断されてしまうため、休業損害の対象とならないのです。
②有給休暇を使ったけれど通院しなかった
有給休暇を使ったけれど通院しなかった場合、休業損害は認められにくいです。
休業損害は、「事故によるケガの治療のために休まなければならなかった」という場合に認められます。
通院していないのであれば、「治療と関係ない理由で休んだ」とみなされ、休業損害が認められない可能性があります。
③交通事故からしばらくして有給休暇を使って通院した
交通事故からしばらくして有給休暇を使って通院した場合、休業損害が認められないことがあります。
休業損害の請求においては、「治療のために仕事を休まなければならなかった」ことが重要です。
事故直後は仕事を休んでいないのに、しばらく経ってから有休を使って通院した場合、「仕事を休んで通院するほどのケガではない」と判断されて、休業損害の対象にならない可能性があります。
休業損害の請求と支払い
休業損害を請求する際の流れや必要書類などについて確認しましょう。
休業損害の請求手続
休業損害を請求する際の手続の流れは下記のとおりです。
【請求手続の流れ】
- 加害者側の任意保険会社に必要書類を提出する
- 加害者側の任意保険会社から休業損害を含めた賠償金が提示される
- 示談交渉で休業損害を含めた賠償金額を決める
- 示談成立後、休業損害を含めた賠償金が支払われる
なお請求手続には、被害者が交通事故によるケガのために実際に休業した事実と、休業による収入の減少を証明する書類を準備しなければなりません。
請求に必要な書類は、下記のように職業によって異なります。
| 職業 | 必要書類 |
|---|---|
| 給与所得者 (パート・アルバイトを含む) | ・休業損害証明書 ・事故の前年分の源泉徴収票 など |
| 自営業者・個人事業主 | ・確定申告書の控え ・医師による就労不能の診断書 など |
| 会社役員 | ・休業損害証明書 ・事故の前年分の源泉徴収票 ・会社の決算書類 など |
| 家事従事者 (専業主婦・専業主夫) | ・家族分の記載がある住民票 ・家事従事者の自認書 ・源泉徴収票、休業損害証明書(兼業主婦の場合) など |
| 無職・失業中 | ・求職活動をしていたことを証する書面 ・内定通知書 など |
| 学生 | ・源泉徴収票、休業損害証明書(アルバイトの場合) ・内定通知書 ・就労時期が遅れたことを証する書面 など |
休業損害証明書の取得方法
休業損害を請求する際に提出する「休業損害証明書」は、交通事故が原因で仕事を休んだ日数や、収入が減少したことを証明するための書類です。
休業損害証明書は、勤務先に記入してもらいます。この際、下記のような事項を正確に記載してもらいましょう。
- ケガにより休業した人の氏名等
- 休業した期間と内訳
- 3ヵ月間の勤怠状況
- 休んだ日の給与の扱い
- 自動車事故による休業がない3ヵ月間の給与
- ほかの給付の受給状況
など
なお、休業損害証明書のひな型は、加害者側の保険会社に依頼すれば送ってもらうことができます。
また、保険会社のWebページでダウンロードできることも多いです。
休業損害が支払われるタイミング
休業損害は、通常、示談成立後に慰謝料などと一緒に加害者側の保険会社から支払われるため、示談成立から1~2週間後のタイミングが多いです。
ただし、休業損害証明書の記載の正確性や保険会社の審査状況により異なる場合があります。
請求する際に注意すべきこと
適切な休業損害を受け取るために覚えておくべきポイントは下記です。
- 実際の収入をもとに計算すること
- きちんと休業損害証明書を書いてもらう
- 重複請求はできない
- 請求期限がある
①実際の収入をもとに計算する
自賠責保険基準では、原則、日額賃金を6,100円として休業損害が計算されます。
もし、1日あたり6,100円以上の収入がある場合には、実際の収入をもとに日額賃金を算出するほうが適切な休業損害を受け取れるでしょう。
加害者側の保険会社から提示された休業損害の額に疑問がある場合は、算出方法を聞いてみるのがおすすめです。
②休業損害証明書に正確な情報を記載してもらう
給与所得者が休業損害を請求するには、勤務先に休業損害証明書を記載してもらう必要があります。
このとき、休業期間中の給与支払いの有無や金額、休業日数、事故前3ヵ月間に支給された給与額といった情報が不正確だと、実際に受け取れる休業損害が減ってしまうおそれがあります。
不備や不足がないかチェックするようにしましょう。
③二重請求はできない
仕事を休んだことで減少した収入の補償には「休業補償」もあります。
ただ、休業補償と休業損害は損益相殺の対象となるため、休業補償として受領した金額を再度、休業損害として受領することはできません。
また、すでに受領している金額については控除する必要があるため注意が必要です。
④請求期限がある
ほかの損害賠償請求権と同様、交通事故の休業損害請求にも時効があるため、一定の期間が過ぎると請求できなくなってしまう可能性があります。
休業損害については、通常、交通事故発生から5年、もしくは症状固定日から5年で時効となります。
ただし、2020年4月1日に新しい民法が施行されたことにより、3年で時効となるものもあるため注意が必要です。
まとめ
交通事故における休業損害は、被害者が事故で働けなくなったために減少した収入を補填する重要な補償です。
ただ、加害者側の保険会社から提示された休業損害が適切な金額とは限らないため、適切な金額や必要書類を把握したうえで手続を進めることが大切です。
弁護士であれば、適切な休業損害を算定のうえ、裁判をしたならば認められる弁護士基準をもとに保険会社と交渉いたします。
また、その他の賠償金についての交渉や手続についてのアドバイスなども可能です。
休業損害について疑問や不安をお持ちの方は、ぜひ交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。
交通事故の被害はアディーレにご相談ください
交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。
弁護士費用特約を利用する方の場合は、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われます。
また、通常は弁護士費用が保険会社の上限額を超えた部分は自己負担となりますが、アディーレにご依頼いただく場合は、保険会社の上限を超えた分の弁護士費用は請求いたしません。
そのため、お手元からのお支払いはないため、安心してご依頼いただけます。
- ※弁護士費用特約の利用を希望する場合は、必ず事前に加入の保険会社にその旨ご連絡ください(弁護士費用特約には利用条件があります)。
【関連リンク】
弁護士費用特約が付いている場合の弁護士費用
弁護士費用特約が付いていない方でも、アディーレ独自の「損はさせない保証」により、保険会社提示額からの増加額より弁護士費用が高い場合は不足分の弁護士費用はいただかないことをお約束します。(※)
また、アディーレへのお支払いは獲得した賠償金からお支払いいただく「成功報酬制」です。(※)
お手元からのお支払いはないため、弁護士費用特約が付いていない方でも安心してご依頼いただけます。
- ※委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
【関連リンク】
弁護士費用特約が付いていない場合の弁護士費用
交通事故被害でお困りの方は、ぜひお気軽にアディーレ法律事務所にお問合せください。